【入社エントリ】僕がmentoに入社した理由とやっていきたいこと
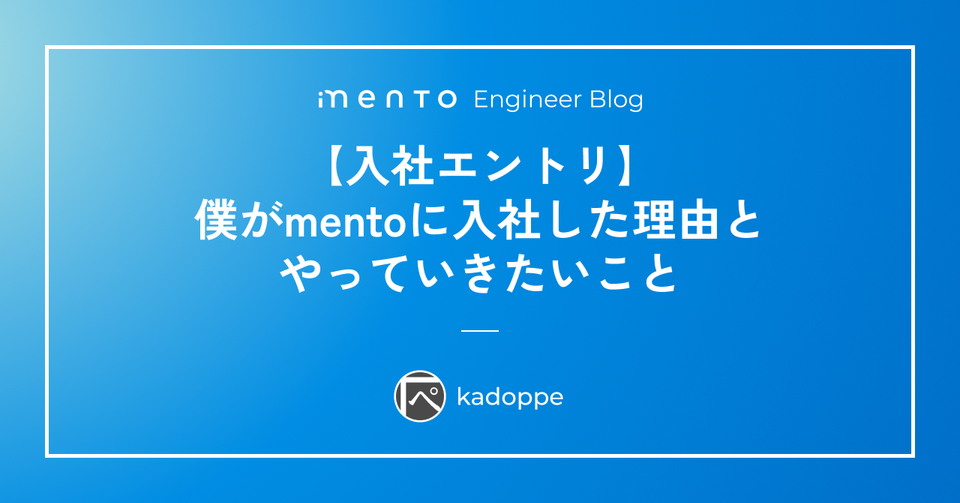
2025年4月、「夢中をふつうにする」をビジョンに掲げ、法人向け・個人向けのコーチングサービスを提供している「株式会社mento」に、ソフトウェアエンジニアとして入社しました。

前職時代の同僚や取引先の皆様には大変お世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
この記事では、僕がmentoに入社した経緯や想いをまとめてみました。少し長文ですが、読んでいただけると嬉しいです。
mento入社までの経緯
コーチングとの出会い
前々職の株式会社プレイドに在籍していた頃、プロダクト開発組織のパフォーマンス最大化を目指す中で、組織や人に強く焦点を当てた、いわゆるマネージメントの仕事をするようになりました。もともと人との対話があまり得意ではなかった僕にとって、かなり難しく悩みも多い挑戦でした。
うまくいかないことも多く、「なにか糸口はないか」と悩んでいたとき、知り合いがちょうど受講していたTHE COACHを知り、思い切って自分もコーチングを学んでみようと決め、基礎コースに参加してみました。
コーチングを学ぶ過程でとくに大きかったのは、「答えは自分の中ではなく、相手自身の中にある」という考え方を身につけられたことです。元々は、対話のなかでつい自分の“正解”を相手に押し付けたり、自分がわからないことをわかろうとして無理に答えを探してしまい、ずっと悩み続けたりすることが多くありました。そういう状況が以前より格段減りましたし、もうそうなってしまったとしても、その深みにハマっている自分自身を客観的に認識できるようになりました。
また、当時のプレイドでは、プロダクト開発組織の規模が急拡大しつつも、フラットな組織構造を維持していたこともあって、誰が何をしているのか、具体的に把握する難易度が上がっていました。相手のやっていること理解できていないからと、本来しっかり話すべき相手との対話のハードルを自分であげてしまい、せっかくの機会を失ってしまったこともありました。
コーチングを学ぶ過程で、たとえ相手のやっていることを僕が詳しく知らなくても、対話を通じて相手の思考や内省を促すことで、相手の中で課題が自然に解決していくことがあることを知り、対話のハードルをぐんと下げることができました。
僕は身の回りに対人・人間関係の課題がある時に、その課題に共感しすぎて四六時中頭から離れなくなり、本来のやりたいこと・やるべきことに集中できなくなってしまうタイプです。コーチングで全てが解決したわけではありませんが、そういった状況に陥ることが減り、本来自分がやりたいこと・やるべきことに集中して取り組みやすくなったと思います。
このような実体験から、僕の中に「コーチングによって、チームや組織で仕事する人たちを助けたり、その人たちが本来やりたかった仕事に集中できる状況が生み出せたりするんだ」という認識が生まれました。
参考:当時の体験について、THE COACHさんから取材いただいた記事
「エンジニアはコーチングを学ぶべき?」ソフトウェアエンジニア・VPoEに聞いてみた | THE COACH ICP™︎(ザコーチアイシーピー)
mentoとの出会い
mentoのCTOであるmatsumatsu20とは、僕がリクルートテクノロジーズに在籍していた時、同じチームで一緒にプロダクトを開発していたこともあり、mentoの存在はかなり早い段階から知っていました。上述したようにコーチングに関する実体験から、僕がコーチングの可能性に魅力を感じており、また以前の同僚が数名mentoに入社していたこともあって、個人的に以前から注目していたスタートアップでした。
2024年3月、matsumatsu20とお互いの近況報告をする中で、ひょんなことから副業 / 業務委託エンジニアとしてmentoに関わることになりました。基本的には週末だけの稼働でしたが、mentoの社内で実際にプロダクトのメンテナンスや機能開発に取り組むことができ、その過程でmentoの理解が少しずつ深まっていきました。
以前は「コーチングサービスを提供している会社」というふんわりしたイメージしかありませんでしたが、実際に中に入ってみると以下のようなことの理解が少しずつ進みました。
- コーチング事業(法人向け・個人向け)の構造や、それを支えるプロダクト・機能群の現状
- コーチングを通して世の中をどのように変えて、どういう価値を提供していきたいのか
- 社内の皆さんがどういう気持ちでビジョンやミッション、コーチングに向き合い、取り組んでいるのか
- エンジニアリングやテクノロジーの力が、現状どのように会社に貢献しているのか、今後どのように貢献・牽引できる余地があるのか
自分が理解できたのはほんの一部だと思います。それでも、実際に中で仕事をすることで、mentoがコーチングやそれ以外の手段を使って、この先の未来にどういった世界を実現し、どういう価値をユーザーに届けようとしているのか、自分の肌で直接感じる貴重な機会になりました。
その後も副業 / 業務委託エンジニアとして継続的に仕事を続けるなか、正式にお誘いをいただきました。それをきっかけに前職を退職することを決め、しばらくの転職活動期間を経たのち、mentoに入社することを決めました。
mentoに入社した理由
mentoの「夢中をふつうにする」というビジョンや、サービスブランドにおける「この国の総労働熱量をあげる」というビジョンに強く共感したことが、mentoに入社しようと決心した一番の理由です。

僕自身、これまでのキャリア(特に30代の10年間)を振り返ると、心の底から夢中に、熱を込めて、本音で働けていたかというと、そうではない時の方が多かったと感じます。「やってみたい」という自分の意思よりも、「組織にとって必要だからやるべきなんだ」という「べき論」や「責任感」を優先させてきました。これは自分の強みでもありますが、40代の次の10年間も同じように働くのでいいのか、自分の意思に向き合わなくていいのか、という葛藤を抱えていました。
僕だけでなく、過去に似た悩みを抱えていた人が他にも何人かいました。近くにいたとあるマネージャーが、いろんな物事の板挟みになり、発生した問題の対処や全体のバランスをとることに多くの時間を使い、結果としてその人本来の特性を発揮できず、やりたいことが全くできない。働くのがとても辛そうな人をたくさん見てきました。
僕自身や、周囲に確かの存在した人たちが抱えていた課題なので、他人事ではなく自分ごととして捉えることができました。この課題を解決し続けることで、ビジョンである「夢中をふつうにする」「この国の総労働熱量をあげる」の実現に繋げていきたいですし、何より自分自身がそういう働き方ができるようなりたいと思いました。
また、副業期間や転職活動期間を通して、mentoのメンバーの皆さんと対話の時間を設けていただく機会をいただきました。その中で、お話した全員が本気でこのビジョンの実現を目指しており、コーチングをはじめとしたmentoが提供するサービスの価値や、ここから会社が進化していくことで生まれる未来の可能性を本気で信じていることがひしひしと伝わってきました。
今の事業や組織の規模・体制、仕事の細かい進め方や制度などは、時間が経てば大きく変わってしまうものです。でも、ビジョン・ミッションは時間が経ってもそうコロコロとは変わりません。自分が強く共感したビジョン・ミッションの実現に向かって、役割や視点は違えど同じ志を持った仲間たちと一緒に取り組める環境は本当に貴重だと思います。うまくいかないことがあったり失敗や壁にぶつかっても、その環境があれば、きっと結果が正解につながるまで諦めずに行動し続けられるはず。そんなことを考えながらmentoに入社することに決めました。
余談:転職活動初期は「組織の成長フェーズ」や「自分に与えられる責務・役職」といった要素も転職先を決める際の軸の一つとして検討していましたが、最終的にはmentoの魅力として感じた「ビジョン・ミッションに強く共感できること」「同じ志を強く持った仲間がいること」の2点が自分の中で圧倒的に大事だと思えるようになりました。
mentoでやっていきたいこと
ここまで、抽象的な内容が多めで、ソフトウェアエンジニアの仕事に関する要素を書いていませんでした。ここからは、これからmentoでソフトウェアエンジニアとしてやっていきたいことを書いていこうと思います。
とはいえ、まだ入社して2週間経っていないので、これからより解像度高めていくフェーズではあります。
当面のミッション:プロダクトの0→1の立ち上げ
mentoは現在、これまで軸となっていたコーチング事業に加えて、新たに管理職をエンパワーメントするプロダクトを生み出そうとしている、まさに0→1の立ち上げフェーズです。
自分はソフトウェアエンジニアとして、このプロダクトの立ち上げを成功させ、事業がPMF以降のスケール期のフェーズに進められるよう、物事を推し進めていきたいです。これまでのエンジニアリングの経験を思う存分活用できればと考えています。
次の事業やプロダクトをどのようなものにするか、探索やヒアリング、仮説検証を並行して進めている段階で、「どう作るか」ではなく「なぜ」「何を」作るかというところから深く議論に参加できるような、立ち上げ初期のスタートアップのような雰囲気の中で、日々みんなで議論をしています。
正社員のエンジニアはCTOや僕を含めて3人とまだ少ないです。その少人数のチームで、決まりつつある次のプロダクトの形を踏まえながら、先に意思決定できる技術設計、アーキテクチャや基盤部分の実装・構築を先行して進めています。
- 開発言語やフレームワークの選定
- 認証認可基盤の設計・構築
- 既存システムのリアーキテクチャと移行
- など
この時期の、制約がほとんどない状況での設計に関する議論は、キャリアの中で意外と経験することが少なく、とても楽しく刺激的な時間になっています。
このプロダクトの0→1立ち上げと並行して、必要に応じて既存のプロダクトの改善やメンテナンスも行います。新しいプロダクトとして作るものが確定したタイミングでは、自分でがっつり手を動かして実装を進めます。
開発生産性の観点でも、開発プロセスやドキュメンテーション、開発環境の整備や、昨今のAIコーディングツールの活用など、多くの伸び代がある状況なので、その辺りの整備も進めています。
要するに状況はいい意味でカオスです。決まっていないことやできていないこと、開発組織としての伸び代がたくさんあり、僕個人としても「無限にやれることがあり、新しい発見によってやれることが毎日増えている」と感じる楽しい日々を過ごしています。
役割や経験にとらわれず、自分の姿を必要に応じて変えながら、一つひとつに焦点を当てながら、物事を着実に前に進めていくことを当面はやり続けたいですし、それがプロダクトが立ち上げを成功させる必要条件だと考えています。
長期的な展望:強い開発組織を作る
mentoのビジョンである「夢中をふつうにする」を、テクノロジーやプロダクトの力でさらに加速させたいです。要するに「仕事で夢中になるのが当たり前」な世界をプロダクトと組織の力で実現したいです。
例えば、現在mentoには、「大量に集まるコーチング記録などの非構造化データを、コーチングの守秘義務を厳守し、プライバシーとセキュリティを最大限考慮した上で、いかに有益な形でユーザーに還元できるようにするか」といった、テクノロジーやプロダクトに関連した面白いテーマ・アイデアがあります。個人的にもとても興味があるテーマです。
他にも面白いアイデアあり、また今後もそういったアイデアがどんどん増えていくでしょう。これらを具現化しユーザーの皆様に価値として届けることで、世の中を変え、mentoのビジョンの実現に向けて一歩近づくことができます。
ここで重要になるのはアイデアを具現化するための、強い開発組織です。自分がイメージする「強い開発組織」とは、以下のような要素を備えた組織です。
- ビジョンやミッション、事業やプロダクトに共感したメンバーが多く在籍していて
- 各自の創造性や専門性を阻害せず、それらを思う存分に発揮できる環境・場があって
- アイデアを具現化し、ユーザーのもとへ届けるサイクルを通して多くを学びとり
- そのサイクルを高速に、高い並列性を持って回し続けることができる
自分がこれまでの経験してきたプロダクト開発組織づくりの経験を活かしつつ、これまでのmentoの当たり前も疑いながら、みんなで議論重ねて、mentoらしい強い開発組織に自分自身も含めて成長してきたい。
まだ「開発組織」と呼べるほどの人数規模ではないので、時期尚早な部分もありますが、採用活動や開発基盤・仕組みづくりなどのできることから始めています。最終的には「mentoといえばテクノロジー・プロダクトカンパニーだよね」と言われるくらいの素敵な開発組織が作れたらいいなと思います。
おわりに
ここまで読んでいただいた方、ありがとうございました。
先に書いた通り、mentoでは僕が「やりたい」「やれる」と思うことが現状無限にあるような状況です。会社はこれからどんどん変わっていき、成長していくフェーズなので、これからもさらにやりたいことは増えていくと思います。
なので、現状は圧倒的に人手が足りません。ソフトウェアエンジニアや、データエンジニア、機械学習エンジニアなどのエンジニア系職種はもちろん、プロダクトマネージャーやデザイナー、さらにはセールスやカスタマーサクセス、HRといったあらゆる職種で人手不足が発生しています。「やりたくてもやれてない」ことがたくさんあります。
もしmentoに少しでも興味を持っていただけた方がいれば、ぜひカジュアルにお話しさせてください。「ちょっと話を聞いてみたい」くらいの軽い気持ちでも大歓迎です。気軽にご連絡いただけると嬉しいです。
「夢中をふつうにする」――このビジョンに共感し、一緒に世の中を変えていきたいと思ってくださる方が増えてくれたら、こんなに心強いことはありません。これからのmentoの挑戦に、ぜひご注目ください。ありがとうございました!
採用情報・サービス情報などはこちら
採用情報


mentoテックブログ
これから記事がたくさん投稿される予定です!

法人向けビジネスコーチングサービス

個人向けパーソナルコーチングサービス

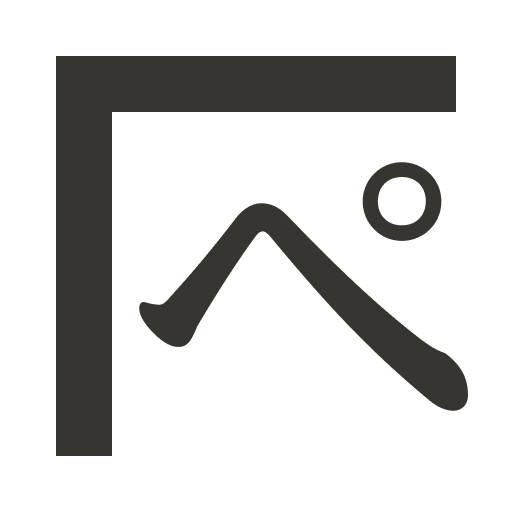



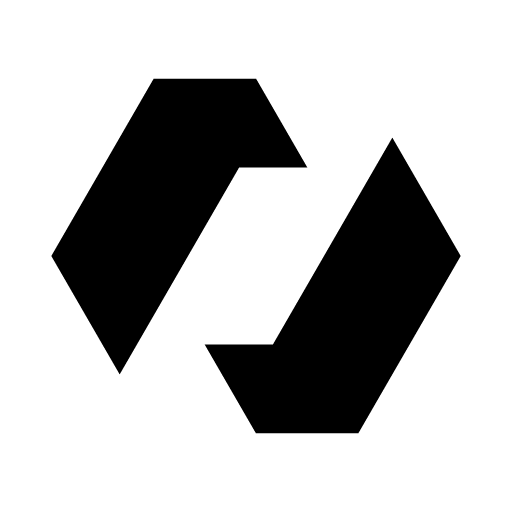
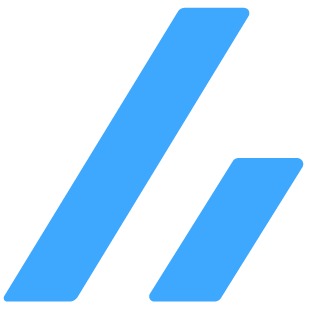

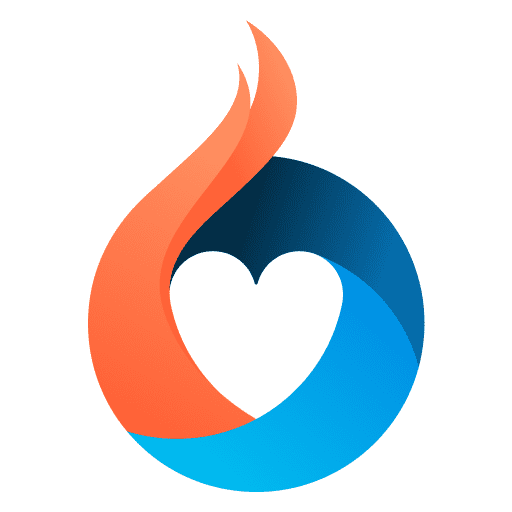
Member discussion