読書:ご冗談でしょう,ファインマンさん 上
どこかのブログ記事で、エンジニアに読んでほしい本としてお勧めされていたので読んでみることにした(肝心の記事を忘れてしまった)。ひとまず上巻のみ読んだ。
一人の技術者として本書を読んでみて、技術者としてこれからの人生もやっていく上で、とても大事なことに気づかされたし、いろんなことを学ぶことができた。以下にいくつか自分個人の体験も交えて書いてみる。
ご冗談でしょう、ファインマンさん (上) (岩波現代文庫 社会 5)
目次
- 1 ふるさとファー・ロッカウェイからMITまで
- 2 プリンストン時代
- 3 ファインマンと原爆と軍隊
- 4 コーネルからキャルテクへ ブラジルの香りをこめて
感想
ノーベル物理学賞を受賞した物理学者、リチャード・P・ファインマン先生の自伝(というのかな?)。ファインマン先生が幼少期の頃や、成長して物理学者になってから、彼が体験した面白いエピソードがユーモアたっぷりに書き綴られている本。
一つ一つのエピソードでは、ファインマン先生自身が遭遇した問題を、どうにか上手く解決する(あるいは、やり過ごしたり、相手をからかったりする)ために、これまで身につけてきた豊富な知識と強い好奇心を活かして、試行錯誤を繰り返していく様子が基本的には描かれている。
「遊ぶ」ことの大事さ
本書の中でファインマン先生は、目の前の問題を解決したり、本質的ではないことにこだわっている人をからかったり、自分の知識欲を満たすために、強い好奇心と「遊び心」を使って、他の人が思いつかなかったり、思いついたとしても決して行動に移すことがないようなアプローチを選択したりする。そういったアプローチを使って試行錯誤を繰り返しながら、物事の核心に近づいたり、誰も気づいていない新たな発見にたどり着いたりする。(時には痛い目に遭ったりもする笑)
ファインマン先生自体に、それぞれの課題を解決することで達成したい「目的」があるにはあるんだけど、ただ「遊ぶ」こと自体も目的化されているような印象を持った。目的と手段がいい意味で一致しているような感じ。思考や行動、選択肢に、「遊び」ならではのぶっ飛んだ要素が加わって、それがユニークな結果につながる一つの要因になっているようにおもえた。
とあるシーンで、ファインマン先生が燃え尽き症候群(?) or スランプ(?)のようになって、研究に身が入らなくなる時期があるんだけど、その状況を打破したのも「遊び心」だった。その時の遊び心で考案した数式が、のちのノーベル物理学賞を受賞するきっかけにもなっていたりする。
思えば、自分も最初は「遊び」からだった。
父親がMSXで入力してくれたゲームのソースコードをいじってみたり、RPGツクールで黒歴史となるゲームを自分で作ってみたり、どうしてもクリアできないHyperCardのゲームをデバッグモードを使ってストーリーをスキップしたり、オンラインゲームのギルドメンバーが交流するためのWebサイトやチャット掲示板を用意したり。いろんな「遊び」を経験しながら、ソフトウェアやインターネットの技術に少しずつ興味を持って、自分で試行錯誤して学んで、この世界にのめり込んでいった記憶がある。
でも、そういう10代や20代前半の「遊び心」も社会人になるにつれて、少しずつ薄れてきたように思う。
仕事でコードを書くことは本当に楽しかった。でも、最初の頃はコードは書けるけどそれ以外の仕事が全然できなくて、たくさんのご迷惑をおかけしていた。運よく色々な経験を積ませてもらって、少しずつ自分でできる仕事が増えたり、クオリティも上がってきた。途中から、仕事の目的を強く意識するようになって、それが自分の仕事から、チームの仕事、組織の仕事、事業の仕事、会社の仕事、のように段々と大きな目的を意識するようになっていった。
いくら目的は大きくなっても、全ては一つ一つの目の前にある課題を解決することの積み重ね。そして、その問題を解決することものすごく楽しかったことのはず。なのに、だんだんその行為自体が楽しむというよりかは、目的を達成するために自動運転的にこなすようことが増えてきた。自分で試行錯誤することが少なくなり、参考になるコードを引っ張ってきて、それを少し応用して、上手く動いて終わり。
それで目的は達成できているのかもしれないけど、一つ一つの問題解決の精度やクオリティはなんとなく若い頃よりも下がってきているような感覚がある。でも、そこに対して強いこだわりや情熱、なんとかしようというモチベーションもそんなに湧いてこない。そして、またどんどんクオリティが下がっていく。20代で培った貯金のようなものを使って、まだなんとかやれているような危機感がある。いつかは底を尽くんじゃないだろうか。
本書を通して、ファインマン先生が「課題で遊んでいる様子」をみて、なんとなく自分が感じていた上記に書いたような危機感の正体が分かったような気がした。「目的意識」を高めることはビジネスをする上で大事なこと。でも、最初の頃に「手段」に感じていた楽しさや「遊び心」を失ってしまっていては、そもそもなんでこの仕事をやっているんだっけ?という自分の存在意義が薄まってしまったり、せっかく身をもって分かっていた「遊び」を通じて色んなことに気づいて学べることを忘れてしまったり、とっても勿体無いことになってしまう。そしてその気づきが学びが、そもそもの目的達成のクオリティをさらに上げることにつながることもあるはず。
一つ一つの問題解決をまた楽しもう。「遊ぶ」ように取り組んで、好奇心を満たして増やして、色んな知識を取り込んで、さらに新しい問題解決を楽しめるようにしよう。目的と手段の距離をもっともっと近づけてみよう。読み終わった後、そんな風に思えた良書だった。
「考えるのことをやめない」ことの大事さ
本書には、ファインマン先生が原子爆弾の研究開発プロジェクトにアサインされていた時のエピソードが掲載されている。
原子爆弾の爆破実験が成功し、ファインマン先生をはじめ、プロジェクトに参加していた研究者や技術者が祝福のパーティで湧きかえっている頃、ボブ・ウィルソンという物理学者がだけが座って塞ぎ込んでいたシーンが描かれていた。以下その内容を引用する。
「何をふさいでいるんだい?」と僕がきくと、ボブは、「僕らはとんでもないものを造っちまったんだ」と言った。 「だが君が始めたことだぜ。僕たちを引っぱりこんだのも君じゃないか。」 そのとき、僕をはじめみんなの心は、自分達が良い目的をもってこの仕事を始め、力を合わせて無我夢中で働いてきた、そしてそれがついに完成したのだ、という喜びでいっぱいだった。そしてその瞬間、考えることを忘れていたのだ。つまり考えるという機能がまったく停止してしまったのだ。ただ一人、ボブ・ウィルソンだけがこの瞬間にも、まだ考えることをやめなかったのである。
R.P.ファインマン; 大貫 昌子. ご冗談でしょう,ファインマンさん 上 (岩波現代文庫) (p.201). 株式会社 岩波書店. Kindle 版.
ここの文章は、本書の中で一番印象に残っている文章。多分しばらく忘れることはないと思う。ゾッとした。ファインマン先生のような「考える」人でさえ、時に考えることを忘れてしまうんだという怖さを感じた。ある範囲や時間を切り取ると「良い目的」だったものが、より広い範囲や長い時間軸で見るとも「ものすごい悪い結果」を生み出すことがあるという一つの例を理解した。
物事の一部しか見えていないのに、今見えているものが全てだと思い込んでしまう。考えることをやめてはいけないと分かっていつつも、もう十分だと自分で判断して考えることをやめてしまう。自分にはそういう癖はある。他の人にもきっとあると思う。
自分の仕事でのアウトプットが、そこまで「ものすごい悪い結果」に繋がるかどうかはわからない。でも、良いと思っていたやっていたことが、知らず知らずのうちに見えていなかった誰かを苦しめたり不利益を与えてしまっていたようなことは、ビジネスやプロダクト開発でも普通に起こり得る。ターゲットユーザーを明確にすることは大事だけど、自分はできるだけできるだけ多くの人にプラスを与えられるようなそういうプロダクトや事業に携わりたい。
だから考えるのをやめないようにしたい。上記に限らず、できるだけ技術者として、解決したい課題のこととや、そのために使える技術のことを考え続けるようにしたい。本書を読んでそんなふうに強く思った。
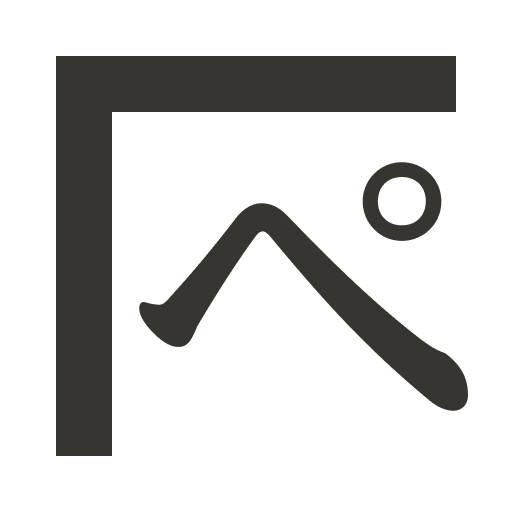
Member discussion